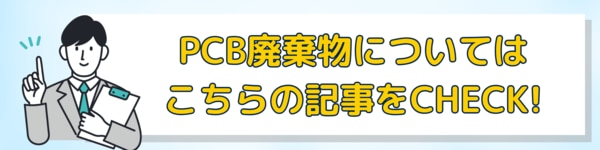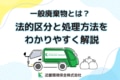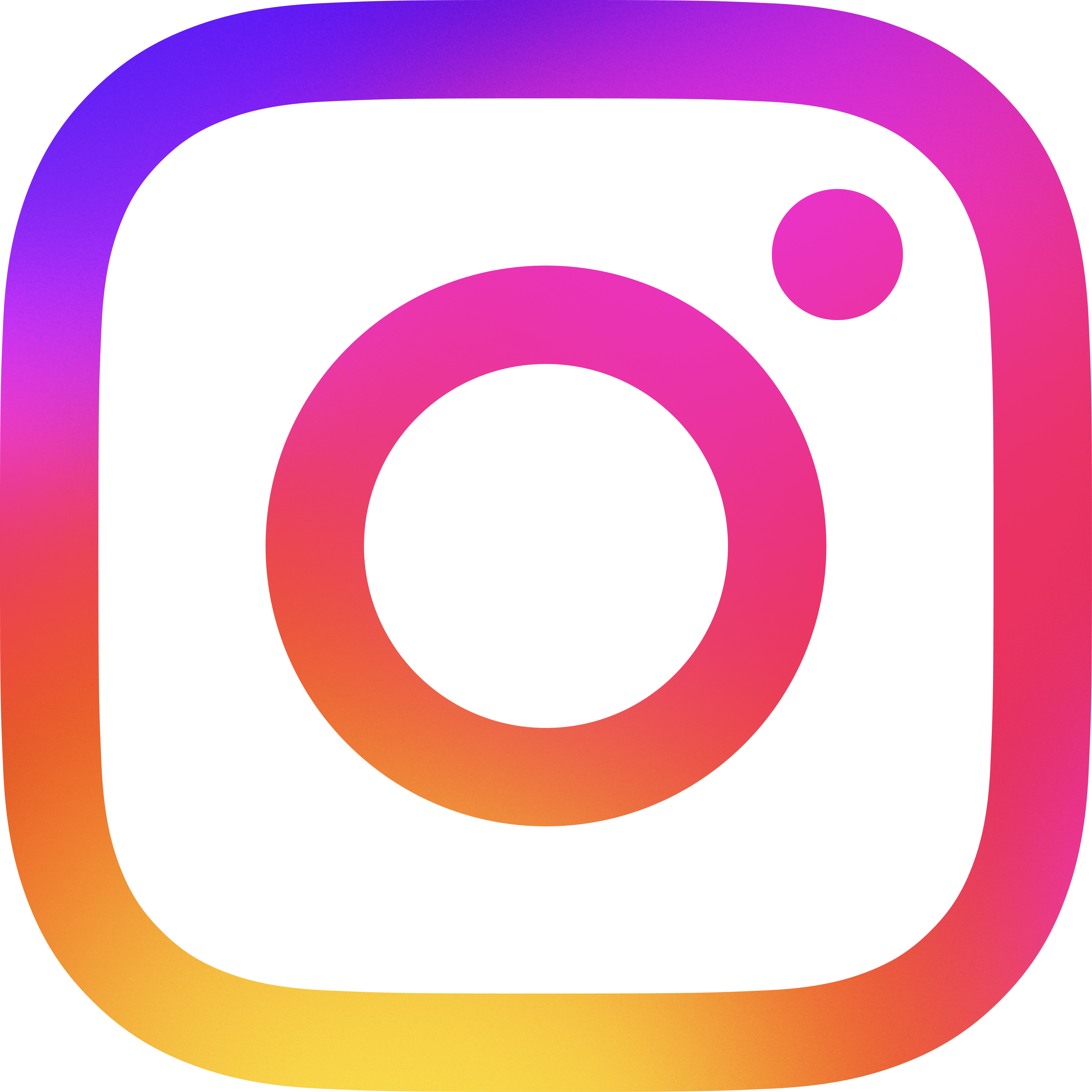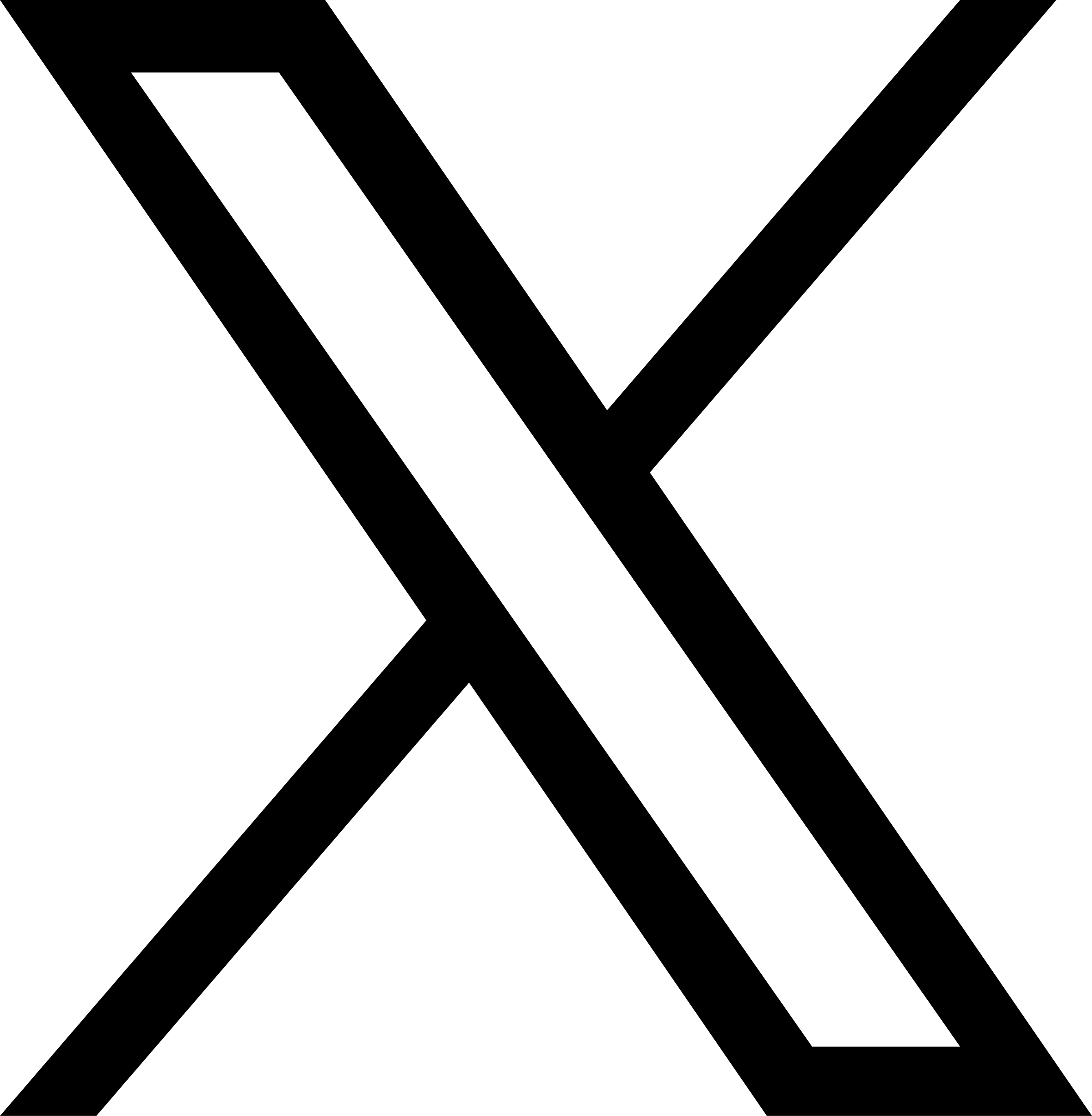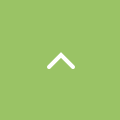産業廃棄物とは?基礎知識から安心できる業者選びのポイントまで紹介!
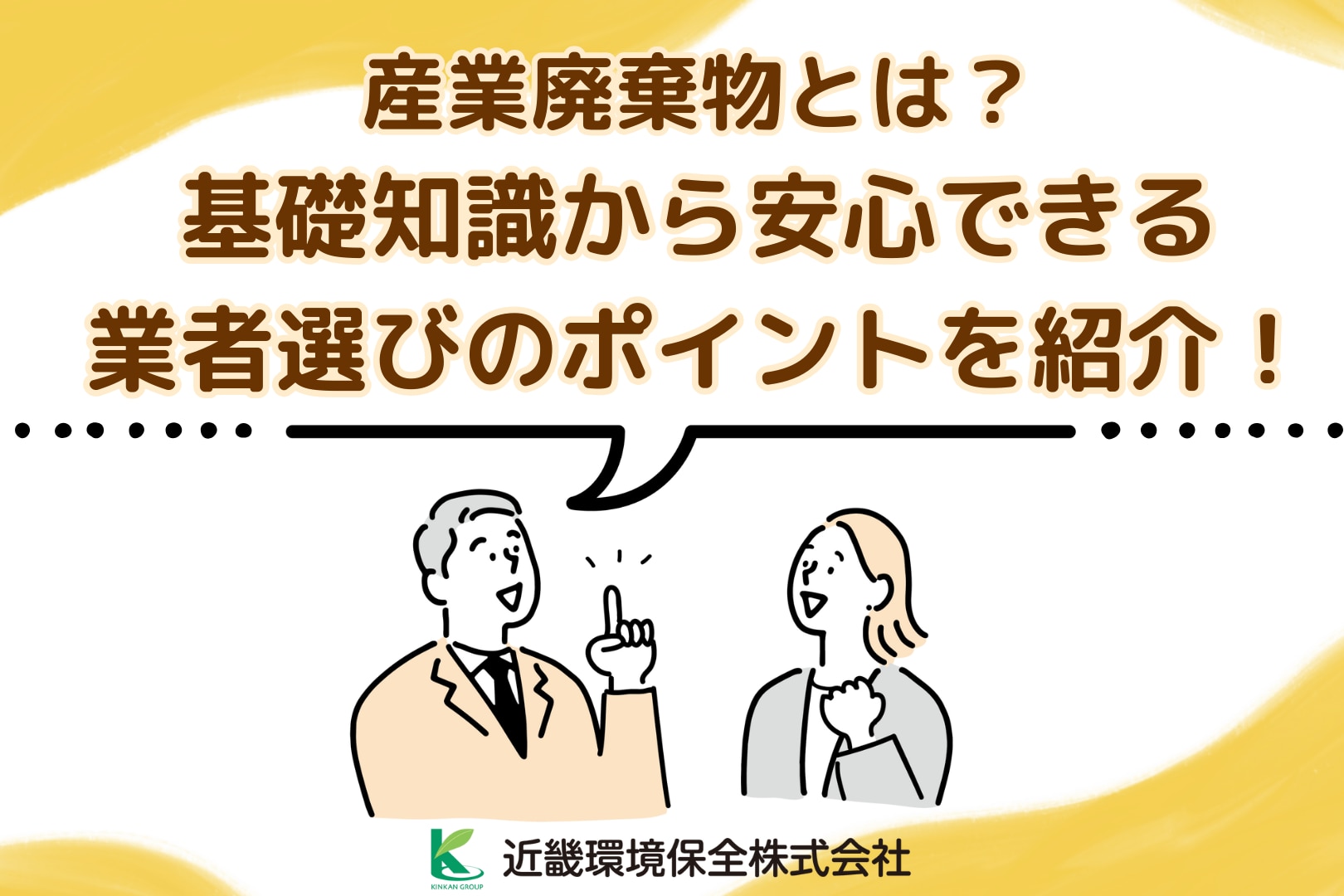
概要
事業活動を行ううえで避けて通れない「産業廃棄物」の処理。
工場や建設現場などから日々発生するこれらの廃棄物は、法令に基づいた適正な管理と処理が求められます。
しかし、「どのようなものが産業廃棄物に該当するのか」「処理時に何に気を付ければ良いか」「業者はどう選べばいいのか」など、分かりづらい部分も多いのが実情です。
本記事では、産業廃棄物の基礎知識から法令上のポイント、業者選びのチェック項目まで分かりやすく解説。
最後には、私たち近畿環境保全が提供する産業廃棄物の適正処理への対応体制についてもご紹介します。
廃棄物の処理でお悩みの企業ご担当者さまは、ぜひご一読ください。
目次[非表示]
産業廃棄物とは何か?

産業廃棄物の定義
私たちの身の回りで日々発生している廃棄物には、実は法律により厳しく分類され、管理が求められているものがあります。その代表格が「産業廃棄物」です。
産業廃棄物とは、工場や建設現場など、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法令で定められた20種類の特定の廃棄物を指します。
たとえば、製造業で排出される廃プラスチック類や、建設業から出る木くずやコンクリートがらなどが該当します。
この分類は「廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」に基づいており、違反した場合には排出事業者が行政処分や罰則を受ける可能性もあります。
そのため、産業廃棄物は品目の確認から保管、最終処理に至るまで、段階ごとに適切な対応が求められます。
さらに、産業廃棄物には有害性や爆発性を持つものも含まれることから、安全な取扱いと法令知識が不可欠です。
排出する廃棄物の性状によって処理方法も大きく異なるため、信頼できる専門業者と連携することが重要となってきます。
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の違い
産業廃棄物の中には、さらに厳重な管理が必要とされる「特別管理産業廃棄物」という区分があります。
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物について、その違いは下記のようになります。
【産業廃棄物】
通常の産業廃棄物には、廃プラスチック類、金属くず、紙くず、木くず、ガラスくず及び陶磁器くず、紙くず、繊維くず、がれき類などがあります。
これらは適切に分別し、許可を持った処理業者によって運搬・中間処理・最終処分されます。
排出事業者は「マニフェスト制度」により処理の流れを把握・管理し、廃棄物の行方を追跡する責任を負います。
これにより、不法投棄や不適正処理を防ぐ仕組みが構築されています。
【特別管理産業廃棄物】
一方、特別管理産業廃棄物とは、毒性・感染性・爆発性・引火性など、人の健康や生活環境に重大な影響を与える可能性がある物質を含んだ廃棄物のことです。
たとえば以下のようなものが該当します。
- 感染性廃棄物(医療機関から排出される血液付着物など)
- 廃油や廃酸のうち、引火性・腐食性の高いもの
- 有害金属(鉛・カドミウムなど)を含む汚泥
- PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む機器類
※PCBについてはこちらの記事をご確認ください
これらの廃棄物は、通常の産業廃棄物よりもはるかに厳しい保管・運搬・処分基準が設けられており、処理を行う事業者にも「特別管理産業廃棄物処理業」としての許可が必要です。
産業廃棄物を処理するときの注意点

保管・運搬時のルール遵守
産業廃棄物は、処理場に搬入されるまでの「保管」および「運搬」の過程でも、法令による厳格なルールが定められています。
これらを怠ると排出事業者にも罰則が科される可能性があるため、細心の注意が必要です。
まず保管については、屋内外を問わず飛散・流出・悪臭の防止措置が義務付けられています。
さらに、保管場所には明確な標識を設け、第三者が誤って接触しないよう配慮することも重要です。
運搬においては、廃棄物の種類や形状に適した車両で、安全かつ確実に搬送する必要があります。
運搬を担う業者には、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必須です。
また、車両には「産業廃棄物収集運搬車」と明記された表示や、許可番号、業者名の掲示が求められています。
これらの表示義務を怠ると、行政指導や罰則の対象になるため注意が必要です。
これらの管理体制が整っていないと、万が一の事故や環境汚染、近隣からのクレームといったリスクにもつながります。
適切な業者との連携、従業員への教育・マニュアル整備などを通じて、確実なルール遵守が求められます。
委託業者の選定は慎重におこなう
廃棄物処理の委託においては、「どの業者に依頼するか」が後々のトラブルや法令違反の有無を左右するため、特に慎重な判断が求められます。
単に許可証を所持しているだけでなく、その業者が信頼に足る対応力を備えているかを多角的に見極めることが大切です。
まず確認したいのは、業者の保有する許可内容と対応可能な廃棄物の範囲です。
自社が排出する廃棄物がその業者の処理対象に含まれているか、処理方法は適正か、事前に細かく確認する必要があります。
次に、過去の実績や処理報告書の提出状況、マニフェスト対応の正確さなどから、業者の説明責任・透明性の高さを確認しましょう。
必要に応じて工場や処分場を実際に見学することも信頼性を判断するうえで有効です。
さらに注目すべきポイントが、「優良産廃処理業者認定制度(いわゆる優良認定)」を取得しているかどうかです。
優良認定を受けた業者は、遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組、電子マニフェストの利用、財務体質の健全性の観点で一定の基準を満たしており、処理の透明性や信頼性の高い業者であることが都道府県・政令市によって認められています。
排出事業者は処理を委託した後も責任を負う「排出事業者責任」があるため、単に価格の安さで選ぶのではなく、安心して長く付き合えるパートナーとして業者を選定する視点が重要です。
マニフェスト制度と記録管理
産業廃棄物を適正に処理するうえで欠かせないのが、「マニフェスト制度(産業廃棄物管理票)」の活用です。
これは、排出事業者が委託した産業廃棄物の収集・運搬から最終処分までの流れを記録・管理するための制度で、法的にも義務づけられています。
この制度の最大の目的は、産業廃棄物の「不法投棄」や「不適正処理」を防止することにあります。
マニフェストには、廃棄物の種類や数量、運搬業者や処理業者の情報、処理完了日などが記載され、処理の各段階で確実に記録・確認が行われます。
これにより、排出事業者は自らが出した廃棄物が最終的にどこでどのように処理されたのかを追跡可能となります。
また、電子マニフェスト(JWNET)の導入が進んでおり、紙による運用と比べて記録の信頼性が高く、管理の効率化・透明性向上にもつながっています。
記録の保管期間は法律で5年間と定められており、監査や行政調査が入った場合にも備えて日常的に正確な管理体制を構築しておくことが重要です。
記載ミスや不備があると、排出事業者自身が行政処分や罰則の対象となる可能性もあるため、業者任せにせず、社内でもしっかりと内容を把握・管理することが求められます。
マニフェスト制度は、単なる帳票のやりとりではなく「自社の廃棄物が適切に処理されているか」を可視化し、社会的責任を果たすための重要な仕組みです。
信頼できる業者と連携しながら、制度の理解と活用を徹底することが、適正処理の第一歩といえるでしょう。
業者選定で押さえるべき3つのポイント

処分したい廃棄物の品目の許可を取得しているか
まず、業者が処分したい廃棄物の品目について、適切な許可を取得しているか調べることが大切です。
許可の範囲外の品目を委託すると、違法となり排出事業者も責任を問われるため、必ず確認が必要です。
許可証の内容は業者によって新規取得等により更新されることもあるため、最新の許可状況を確認することも重要です。
また複数品目を取り扱う場合は、それぞれの品目に対する許可がきちんと揃っているかチェックしましょう。
適正金額で収集運搬及び処理をしているか
価格は重要な判断材料ですが、あまりに安すぎる場合は注意が必要です。
安価な料金設定は、法令違反や不適切な処理を伴うリスクが潜んでいることがあります。
排出事業者は適正なコストを支払うことで、安全かつ確実な処理が保証され、将来的なトラブル回避につながります。
弊社のように収集運搬とグループ内の中間処理会社が連携している場合、コスト面でも透明性が高く、無駄を省いた効率的な運用が可能です。
見積もりの内訳をしっかり確認し、不明瞭な点がないかを確認することも大切です。
優良認定を受けているか
優良産廃処理業者認定制度の取得は、法令遵守や環境配慮、安全管理に優れている証明です。
優良認定を受けている業者は、適正な処理を確実に実施し、排出事業者のリスク軽減にもつながります。
信頼性や安心感を求めるなら、この認定は重要な指標の一つです。
また優良認定を受けている業者は、許可証の有効期限が通常より長く設定されているため、自社内での業者の許可証管理もスムーズになります。
選定の際は、ISOなど他の認証と併せて総合的にチェックすることをおすすめします。
まとめ|KINKAN GROUPに任せる価値とは?

これまでにご紹介したように、産業廃棄物処理業者を選定する際には確認を怠ってはならない様々なポイントがあります。
これらを確認して業者選定を行うことは排出事業者としてのリスク回避につながります。
しかし、法令や許可品目やエリア、処理方法まで確認しながら業者を選ぶのは、時間も手間もかかる作業です。
そんな時こそ、確かな実績と体制を持ったパートナーを選ぶことが重要です。
そこで私たちKINKAN GROUPは、下記のような6つの強みをもとに、排出事業者様を力強くサポートします。
ワンストップで対応できる安心体制
近畿環境保全はメインである収集運搬業務に加え、グループ傘下に中間処理施設である、湖南リサイクルセンターを保有しており、収集から中間処理までを一括して対応可能です。
これにより、契約手続きやマニフェストの一元管理が可能となり、手間の削減とトラブル防止に大きく貢献します。
処理困難物にも強い専門性
PCBやアスベストなど、法令上の扱いが厳しかったり処理方法や処理場所が限られる廃棄物にも、調査から収集運搬及び処分までをトータルサポートできる体制を整えています。
PCB調査士やアスベスト調査士が在籍し、専門性を活かした安心安全な処理が可能です。
優良認定と強化された体制
優良産廃処理業者認定はもちろん取得済みで、ISO 14001など複数の認証も取得しています。
これらはコンプライアンス・環境配慮・安全管理体制の厚さを裏付けています 。
安定した継続力とサポート
事業継続力強化計画の認定を受けており、災害時にも途切れずサービスを提供できる体制を構築。
豊富な搬出先を確保することにより、処理が停滞してしまうリスクも最小化しています。
循環型社会へ貢献するリサイクル対応
廃棄物は可能な限り埋立に頼らず、リサイクル処理を行います。
また、99%再生材を使用したごみ袋FUROSHIKIの取り扱いを行っており、マテリアルリサイクルやカーボンニュートラルへの取り組みにも積極的に貢献しています。
地域密着・実績豊富な信頼基盤
創業60年以上、3,000社以上との取引実績を有する確かな信頼があります。
滋賀・京都を中心に関西圏はもちろん、全国各地にわたる広範な活動エリアと、地域経済を支える姿勢にも評価のお声をいただいています。
近畿環境保全では、複雑化する廃棄物処理業務を確実・丁寧に、そして安心してお任せいただける体制を整えてお待ちしております。