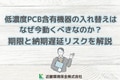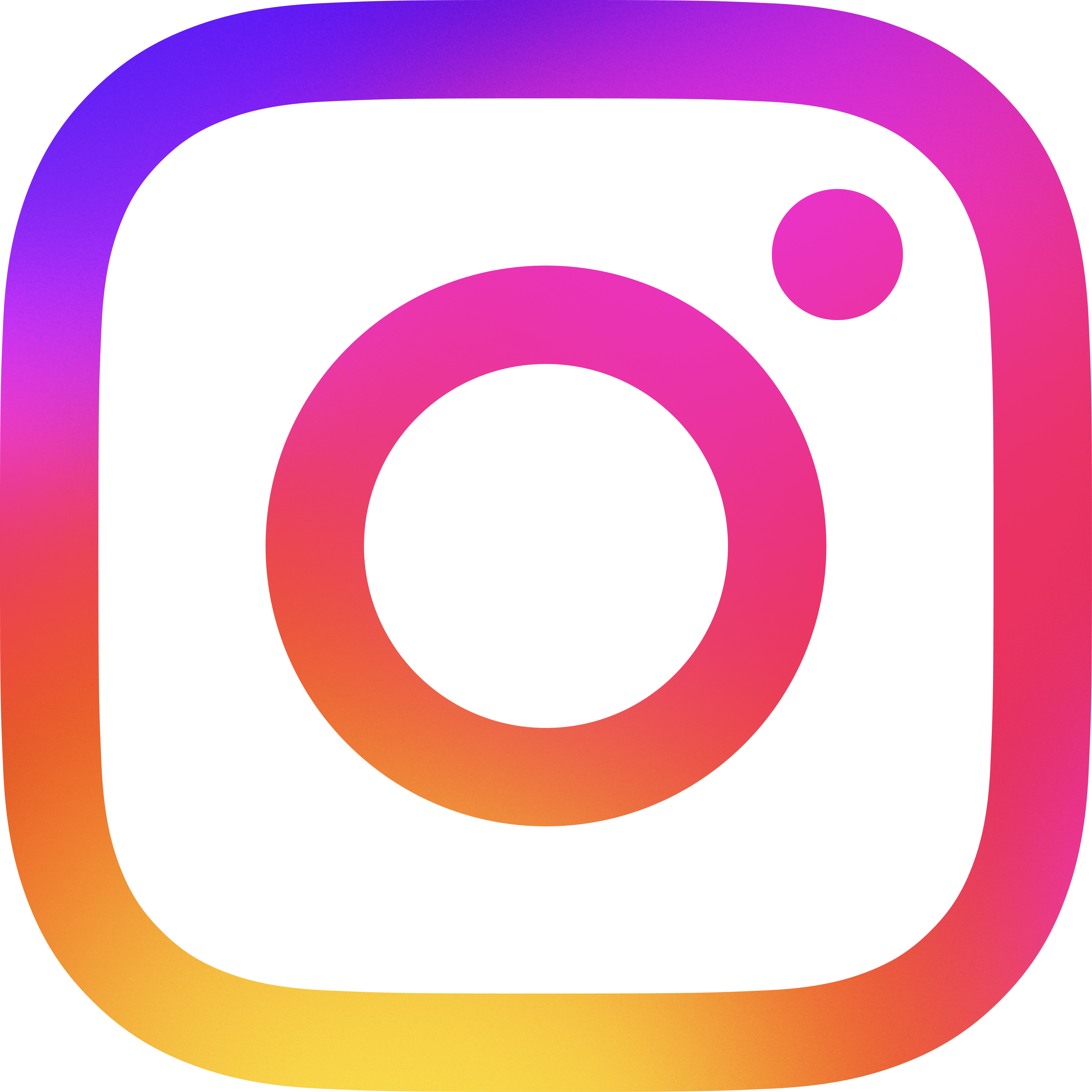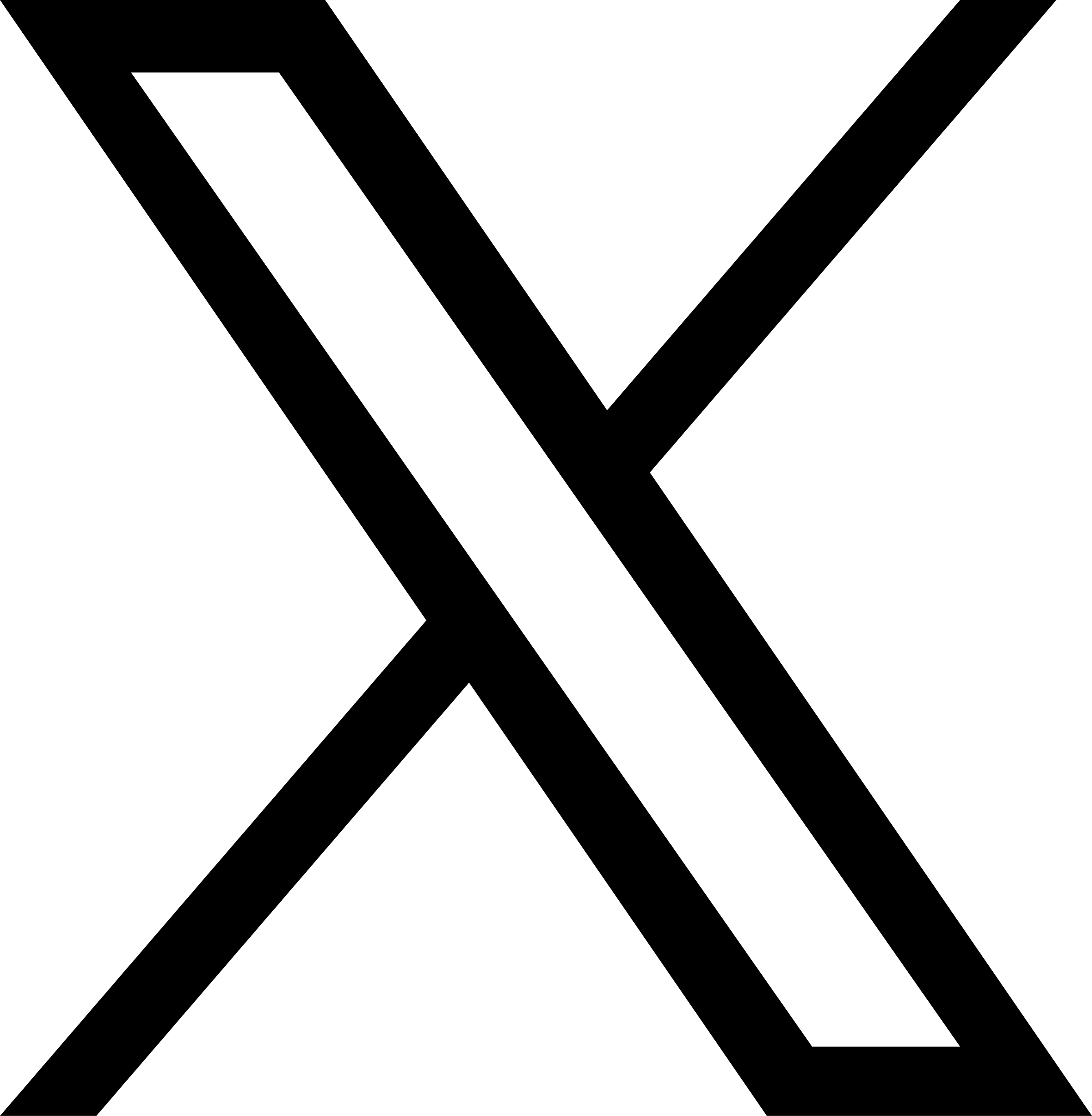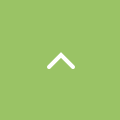産業廃棄物処理委託契約書の必須事項と作成の注意点
産業廃棄物の処理を外部に委託する際に欠かせないのが、「産業廃棄物処理委託契約書」です。
これは法律で締結が義務づけられており、内容に不備があると排出事業者・処理業者の双方が行政処分の対象となる可能性もあります。
にもかかわらず、実務の現場では「前回の契約書をそのまま流用している」「細かい内容まで理解していない」というケースも少なくありません。
本記事では、契約書に盛り込むべき必須事項や作成時の注意点、そして法令遵守のための管理方法について詳しく解説します。
正しい契約書の理解と運用が、企業のコンプライアンスと信頼を守る第一歩となります。
なぜ「産業廃棄物処理委託契約書」が必要なのか

契約書は「法律で義務づけられている」
産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は「廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」に基づき、処理業者と書面による契約を結ばなければなりません。
これは同法第12条第5項で明記されており、委託契約書を交わさずに処理を行うことは違法行為となります。
この契約書は、廃棄物の種類・数量・処理方法・委託範囲などを明確にするものであり、適正な処理が確実に行われるための根拠書類です。
たとえ長年取引のある業者であっても、口頭での取り決めやメールのやり取りだけでは法的効力が認められません。
また、契約内容が曖昧なまま委託を行うと、仮に不法投棄や不適正処理が発生した場合でも、排出事業者が「委託責任」を問われるリスクがあります。
廃棄物処理法は「排出者責任」の原則に基づいており、契約書はその責任を適正に果たすための最初のステップです。
したがって、契約書は形式的なものではなく、企業のリスクマネジメントの一環として正確に作成・保管する必要があります。
委託契約書がないことで起きるリスク
契約書を交わさずに委託を行った場合、行政処分・罰則の対象となる可能性があります。
廃棄物処理法違反と判断されると、排出事業者・処理業者の双方が「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科されるケースもあり、企業名の公表という重大なリスクにもつながります。
実際、環境省や自治体の公表事例をみると、「契約書の不備」「再委託禁止違反」「契約期間切れの放置」など、書面管理の不徹底が原因で処分を受けたケースが多く見られます。
また、契約書がないと処理責任の所在が不明確になり、万一の事故やトラブル時に「どちらが責任を負うのか」が争点になります。
不法投棄や環境汚染の問題が発生した場合、たとえ自社が関与していなくても、「適正な委託管理を怠った」と見なされる恐れもあります。
このようなリスクを回避するためにも、契約書の作成・更新・保管を徹底することが、企業の社会的信用を守る上で欠かせません。
契約書に必ず盛り込むべき「必須事項」

委託契約書で定めるべき基本項目
委託契約書には、法令で定められた「記載すべき必須事項」があります。
代表的なものは以下の通りです。
- 排出事業者および受託業者の氏名(名称)・住所・代表者名
- 廃棄物の種類、数量、性状
- 処理の方法(収集運搬、中間処理、最終処分の別)
- 契約期間
- 契約の解除条件
これらは廃棄物処理法施行規則第8条で定められており、1つでも欠けると契約としての法的効力が不十分になる可能性があります。
特に「廃棄物の種類・性状」は、処理方法を左右する重要な要素であり、曖昧な表現は避けるべきです。
近畿環境保全では契約期間を基本的に自動更新としていますが、取引が5年間ない場合には契約を終了する運用を採用しています。
契約内容は定期的に見直すことで、処理体制や契約条件の現状とのずれを防ぎ、トラブルを未然に防止することが可能です。
これらの項目を正確に記載することで、委託範囲と責任を明確にし、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
特に注意が必要な「中間処理・再委託」に関する記載
委託契約書を作成する際に特に注意すべきなのが、「再委託」に関する取り決めです。
再委託とは、受託した業者がさらに別の業者に処理を委ねることを指します。
廃棄物処理法では、原則として再委託は禁止されており、やむを得ず行う場合には排出事業者の書面による同意が必要です。
このため、契約書には「再委託の可否」や「再委託先の責任範囲」を明確に記載しなければなりません。
記載が不十分だと、再委託先で発生した不適正処理についても、排出事業者が責任を問われるリスクがあります。
また、中間処理業者に委託する場合には、「どの工程までが中間処理で、どの工程が最終処分なのか」を具体的に明記しておく必要があります。
中間処理後の残さ(処理残渣)の取り扱いも重要なポイントであり、「最終処分まで責任を負うのか」「誰が搬出するのか」を明確にしておくことがトラブル防止につながります。
実務上も、契約書の雛形をそのまま流用せず、委託実態に即した形で更新していくことが重要です。
「化学物質情報(PRTR/化管法)」への対応

改正された「契約書記載事項」に加わる化学物質情報
具体的には、以下の場合において、契約書に化学物質に関する情報を記載することが義務化されます。
排出事業者が 化管法(PRTR制度)における第一種指定化学物質等取扱事業者 に該当する場合
委託する産業廃棄物に「第一種指定化学物質」が含有または付着している、あるいはその可能性がある場合
記載すべき内容は、次のとおりです。
当該化学物質の名称
その化学物質が含まれている量または割合
含有または付着していること自体を明記
この追加記載事項は、契約書の透明性を高め、事業者間で化学物質の移動や処理に関する情報共有を確実にする意図があります。
ただし、この規定の 施行日 は令和8年1月1日からであり、改正前に締結された契約書には、改正前規定が適用される経過措置があります。
実務で押さえるべき対応ポイントと注意点
この改正対応を契約書に落とし込む際には、次のような点に注意する必要があります。
排出事業者の判断基準の確認
排出事業者が PRTR 対象事業者に該当するかどうかを確認し、そもそも化学物質情報の記載が必要となるケースかを見極める。分析または見積もりによる情報把握
実際に化学物質が含有・付着しているかどうかの判断には、成分分析や推計が必要になる場合がある。
そのため、排出事業者と処理業者間で事前にサンプル調査や情報交換が必要。記載形式・記載精度のルール設計
「量または割合」の記載方法を統一ルールで定め、誤差や推定値で記載する場合のルールも契約条項に明記しておくべき。情報更新義務・通知義務を設ける
契約後に化学物質の添加、混合物の変更などがあったときに、速やかに通知・契約の修正を行う条項を設けること。適用除外と負担調整
化学物質の含有可能性が極めて低いと判断される場合の除外条件や、調査コストを見込んだ負担分担条項(分析費用の按分など)も検討しておく。
このように、新しい規定を契約書に反映させる際には「形式的な記載にとどまらず、実態に即した協議と運用設計」が重要となります。
契約書作成・管理で押さえておきたいポイント

電子契約の活用とメリット
近年、契約書を紙ではなく電子契約で交わす企業が増えており、当社でも電子契約の活用を推奨しています。
電子契約には、紙の契約書に比べて多くのメリットがあります。
まず、印紙税が不要となるためコスト削減につながります。
また、契約書の保管や検索がクラウド上で簡単に行えるため、管理業務の効率化や紛失リスクの低減にも効果的です。
さらに、電子契約では契約更新や締結状況を自動で管理できる機能もあり、契約の見落としや更新忘れを防止できます。
契約当事者全員の署名やタイムスタンプが付与されるため、法的効力も紙の契約書と同等です。
廃棄物処理法上、契約内容の提示が求められた場合でも、電子署名付きで保存されていれば問題なく対応できます。
このように、電子契約は「法的要件を満たしつつ、管理効率と安全性を両立できる」仕組みとして非常に有用です。
近畿環境保全では、契約書の電子化を積極的に推奨しており、取引先様にも安心・安全にご利用いただける運用体制を整えています。
紙の契約書と比べ、迅速な締結・更新と、管理業務の大幅な効率化が可能な点が大きな魅力です。
更新・管理の徹底で「コンプライアンス維持」
契約書を一度作成しただけで安心してはいけません。
契約期間の切れた契約書を放置していると、知らないうちに「無契約委託」となり、法令違反となるケースがあります。
特に、収集運搬と中間処理・最終処分を別業者に委託している場合は、それぞれの契約書を個別に管理する必要があります。契約更新のタイミングを一覧管理できる台帳やシステムを導入することで、期限切れを防ぐことができます。
また、処理内容や業者の変更があった際には、その都度契約書を見直すことが重要です。
年に1回、契約書内容を精査する運用を行うことで、法改正への対応漏れも防止できます。
企業のコンプライアンス体制を維持する上では、「契約書の整備と更新管理」は欠かせない要素です。
社内でのチェック体制を整え、排出事業者としての責任を果たす体制を構築しましょう。
契約書の作成もお任せください

当社のサポート体制
近畿環境保全では、産業廃棄物の収集運搬から中間処理、さらに自社で対応が出来ない廃棄物であってもネットワークを駆使し、適正な処理までのサポートを一貫して行っています。
契約書の作成において不明点が多い場合は、排出事業者様に代わり、弊社で契約書を作成することも可能です。
もちろん自社の契約書だけではなく、近畿環境保全を窓口として他社に処理を依頼する場合においても、他社との契約書のやり取りも全て近畿環境保全が管理を行います。
また、法改正や行政の運用方針の変化にも対応し、常に最新の法令遵守を実現できる体制を整えています。
「契約書をどう作ればいいかわからない」「現状の契約内容で問題がないか確認したい」といったご相談にも対応しております。
適正処理の第一歩は、正しい契約書の整備から。ぜひお気軽にご相談ください。