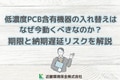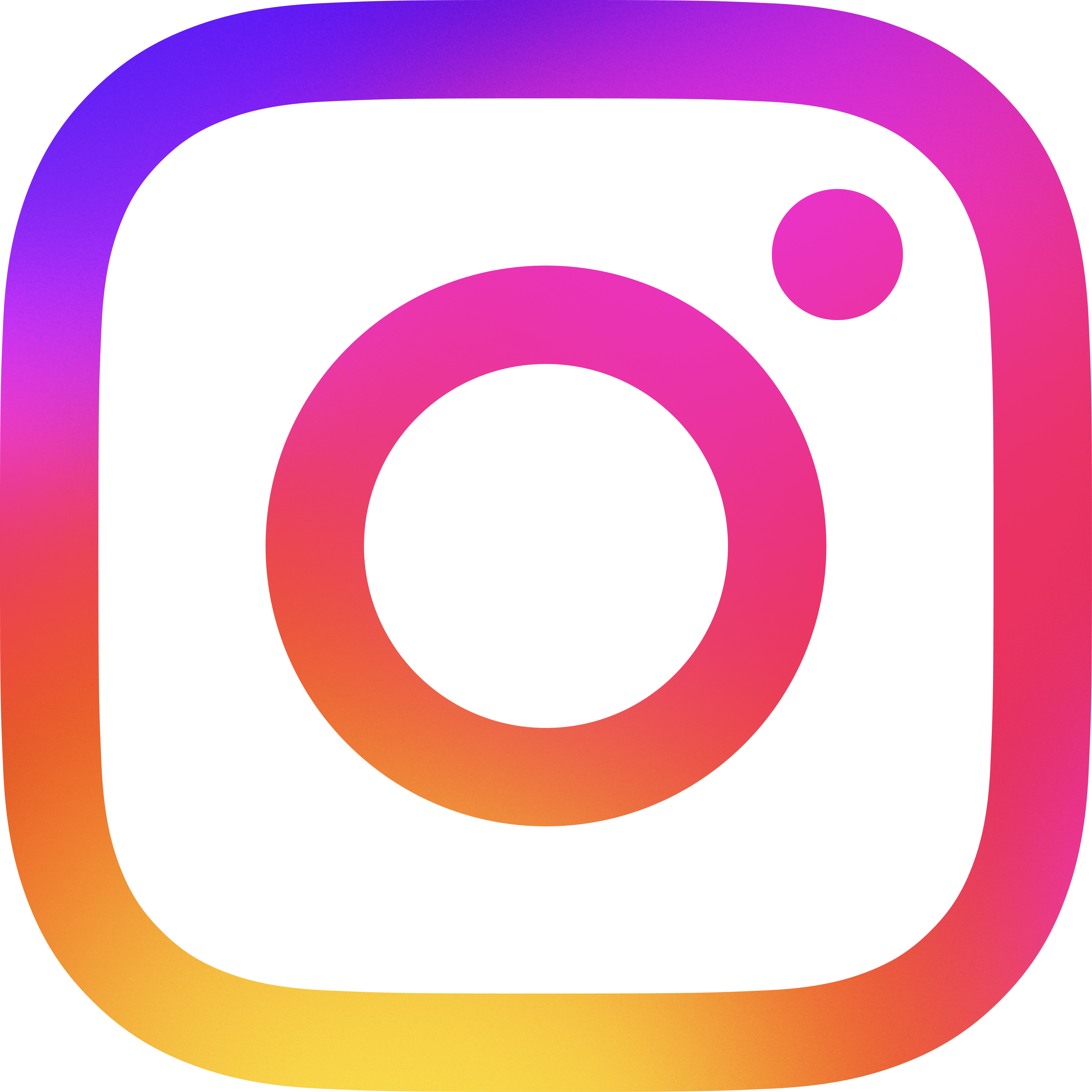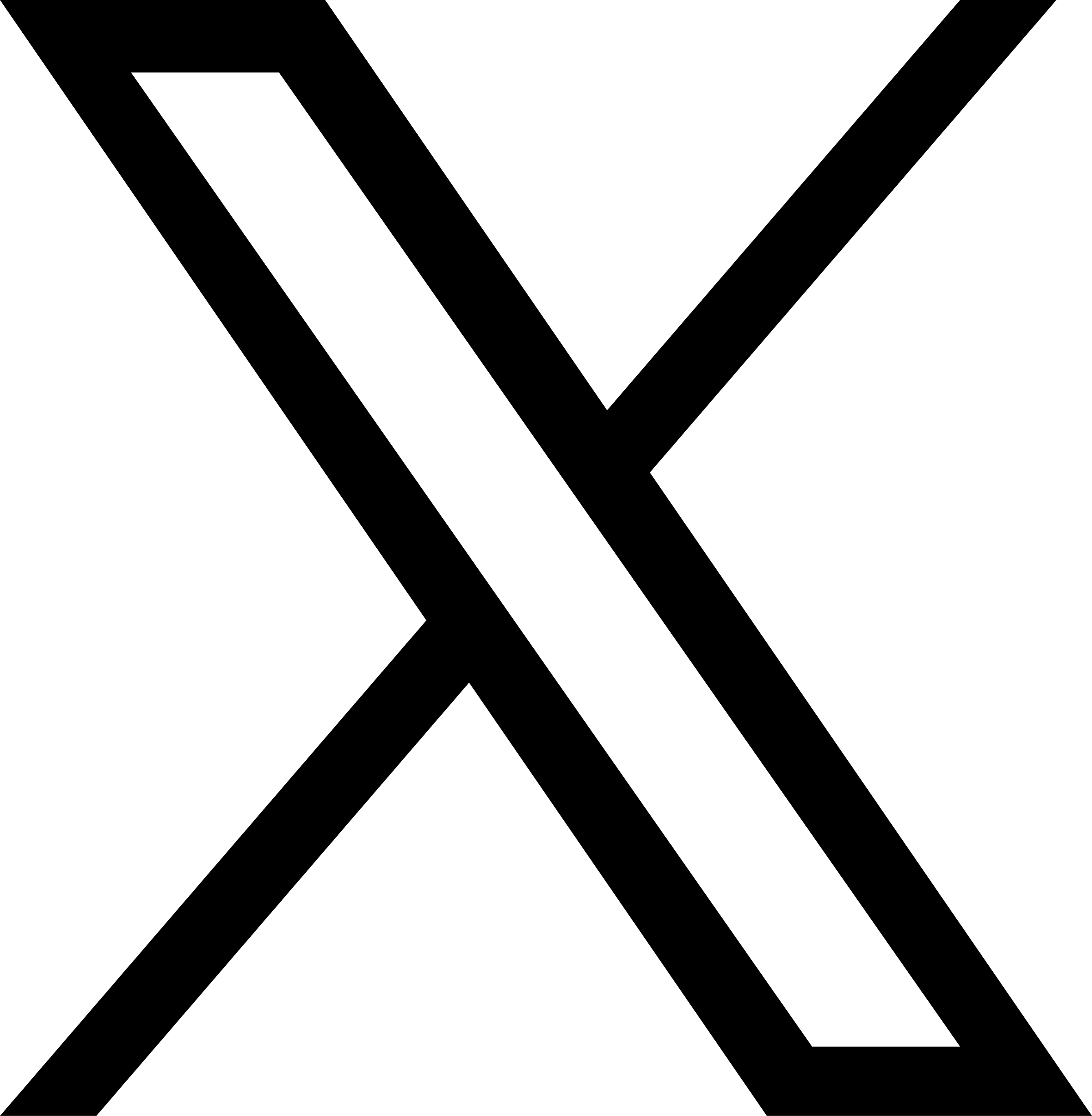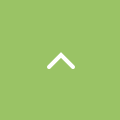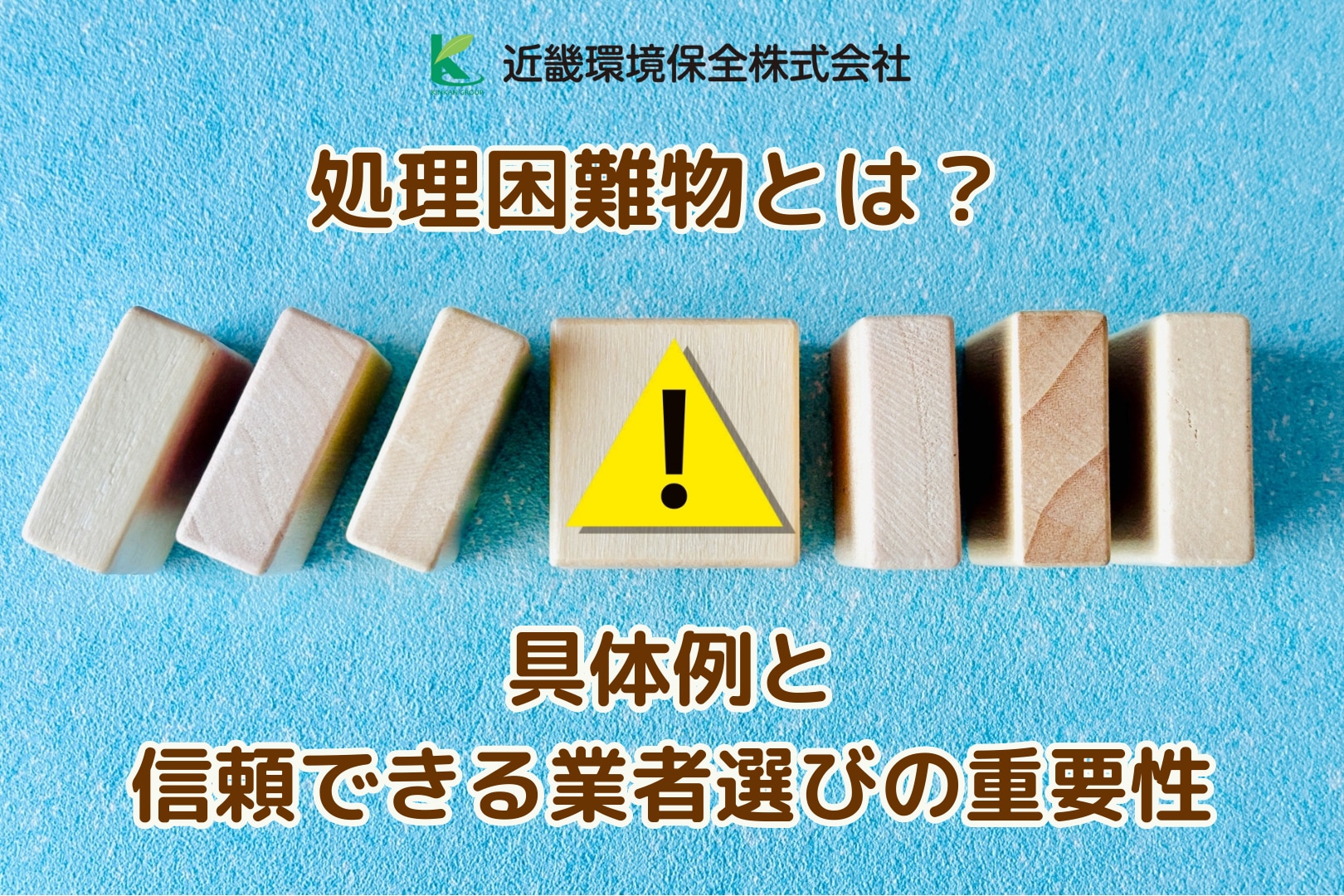
処理困難物とは? 具体例と信頼できる業者選びの重要性
産業活動から発生する廃棄物の中には、通常の処理施設では簡単に処理できないものがあります。
そういった廃棄物を「処理困難物」と呼びます。
処理困難物は性状や成分が特殊であるため、通常の焼却や埋立では安全性が確保できず、専用の処理設備や高度な技術が求められます。
排出事業者はこうした廃棄物を適切に処理する義務を負っており、もし不適正に処理した場合は、法的責任や企業イメージの失墜といった重大なリスクを背負うことになります。
本記事では、代表的な処理困難物の種類と処理方法、排出事業者が押さえるべきポイントについて解説します。
処理困難物の実例

廃液系(廃油・廃酸など)
廃液系の処理困難物には、廃油や廃酸・廃アルカリといった液状の産業廃棄物が含まれます。
これらは一見すると単純に見えますが、処理工程においてさまざまなリスクを伴うため、専門的な対応が欠かせません。
たとえば廃油は燃料としての再利用が可能な場合もありますが、種類によっては異物が混入していたり、有害物質を含んでいるケースもあります。
廃酸や廃アルカリは強い腐食性を持つことから、輸送や保管の段階で容器の劣化や漏洩が起きる危険性があります。
また、これらを中和処理する際には、化学反応による発熱やガスの発生が想定されるため、安全対策を徹底する必要があります。
さらに、こういった廃液は下水や公共用水域に流出した場合、環境に深刻な影響を与える可能性が高いため、厳しい法規制の対象となっています。
廃棄物処理法だけでなく、水質汚濁防止法や消防法など複数の法令にまたがる管理が必要になることも少なくありません。
排出事業者は、発生した廃液の性状を正確に把握し、それに適合した処理フローを選定することが求められます。
専門の処理施設では、中和や固化、焼却、蒸留などの工程を組み合わせ、環境負荷を最小限に抑えながら処理が進められています。
こうした廃液の取り扱いは、一般的な廃棄物よりも高い専門知識と設備が不可欠であるため、処理困難物として位置づけられているのです。
汚泥系(水分や粘度が高い汚泥など)
汚泥は、建設現場、下水処理施設、製造工場など幅広い場所で発生します。
水分を多く含む性質や、粘度の高さによって取り扱いが難しいものは「処理困難物」に該当します。
たとえば建設現場で発生する掘削土の中には、細粒分が多く含まれて水分を保持しやすいものがあり、通常の脱水処理では処理効率が極端に悪くなることがあります。
また、工場から排出される汚泥の中には油分や有機物が混在しており、単純な焼却や埋立てでは対応できません。
このように、汚泥の性状は発生源によって大きく異なるため、処理方法の選定が非常に重要になります。
汚泥の処理には、まず含水率を下げる「脱水工程」が不可欠です。
フィルタープレスや遠心分離機などを用いて水分を除去し、体積を縮小させることで後工程の効率を高めます。
しかし、水分が多すぎる場合や油分・化学物質を含む場合は、機械的な脱水では十分に減容できないことが多く、薬品を加えて凝集させたり、安定固化材を混合して処理する方法が採られます。
また、焼却する際にも高含水汚泥は発熱量が不足し、補助燃料が必要になることがあります。
このような点から、汚泥系の産業廃棄物はコスト負担が大きく、排出事業者にとってもリスクの高い存在です。
適正処理を行うには、性状分析をきちんと行ったうえで、実績のある処理業者に委託することが不可欠となります。
有害物質系(重金属など)
重金属を含む産業廃棄物も、代表的な処理困難物の一つです。
鉛、カドミウム、水銀、六価クロムといった有害金属は、環境中に放出されると人体や生態系に長期的な悪影響を及ぼします。
たとえば、鉛は神経系に障害を与える可能性があり、水銀は水俣病の原因物質として知られています。
こうした重金属は分解することができず、自然界に残り続ける性質を持つため、通常の焼却や埋立てでは安全性を確保できません。
そのため、処理には高度な技術が求められ、管理型あるいは遮断型といった厳格な基準を満たす最終処分場での対応が必要になります。
処理工程では、重金属を安定した化合物に変換し、溶出しにくい状態にする「安定固化処理」や、薬剤による中和・沈殿処理が行われることがあります。
また、焼却施設で処理する際には、排ガス中に有害金属が飛散しないよう、高性能の集じん装置や排ガス処理設備が必須です。
排出事業者が注意すべき点は、こうした有害物質系廃棄物を一般の産業廃棄物と混在させないことです。
混合させてしまうと適正な処理ルートが取れなくなり、環境事故のリスクが高まります。
重金属を含む廃棄物を扱う際には、事前の分析と分類が欠かせず、専門知識を持つ処理業者に委託することが法令遵守と企業リスク低減につながります。
処理方法の概要

処理困難物は、その種類ごとに専用の処理方法が必要です。
廃液は中和・蒸留・焼却といった化学的処理が中心となり、汚泥は脱水・固化・焼却などを組み合わせることで処理されます。
有害物質を含む廃棄物は、安定固化や専用の処分場での隔離保管が不可欠です。
いずれの場合も、一般的な処理施設では対応できず、高度な設備を持つ専門施設に委託することが前提となります。
また、処理フロー全体を通じて「環境への影響を最小限に抑えること」が最重要であり、排出事業者自身も性状分析や適切な分類を行い、処理業者に正確な情報を提供することが必要です。
さらに、処理困難物は高度な専門知識と経験を要するため、対応できる運搬業者や処理業者は限られています。
運搬時の事故防止や処理工程での安全管理を徹底するには、専門的な技術や設備が不可欠だからです。
そのため、委託先を選定する際には、単に許可を持っているかどうかだけでなく、優良認定の取得状況や過去の処理実績、法令遵守体制などを総合的に確認することが重要です。
信頼性の高い業者に依頼することが、最終的には排出事業者自身のリスク低減につながります。
排出事業者の責任
廃棄物処理法では、処理を委託した後も「排出事業者責任」が明確に定められています。
つまり、処理業者に任せたからといって責任が消えるわけではなく、最終処分が適正に完了するまで責任を負わなければなりません。
マニフェスト制度によって処理の流れを記録し、最終処分の確認を行うことが排出事業者に求められています。
不適正処理が発覚した場合、行政処分や罰則だけでなく、企業の社会的信用が大きく損なわれるリスクもあります。
そのため、処理困難物の委託先を選定する際には、許可の有無や実績、処理能力を慎重に確認することが欠かせません。
まとめ

処理困難物は、通常の廃棄物と比べて処理方法が複雑であり、排出事業者にとって大きなリスクを伴います。
廃液、汚泥、有害物質といった処理困難物に対して、適した処理工程を理解し、信頼できる業者に委託することが不可欠です。
企業が法令を遵守し、環境への責任を果たすためには、処理困難物への正しい知識と対応力が求められます。
適正処理を行うことは、企業の社会的責任を果たすだけでなく、持続可能な社会づくりにも直結する取り組みです。
近畿環境保全は、産業廃棄物処理に関する優良認定を取得しており、廃液や汚泥、有害物質といった処理困難物にも豊富な対応実績があります。
収集運搬から最終処分まで一貫してサポートできる体制を整えており、法令遵守と安全管理を徹底したサービスをご提供しています。
「これはどうやって捨てたらいいんだろう?」「他社に断られた廃棄物がある」「処理方法が分からず、放置しているものがある」など、処理困難物の対応にお困りの際は、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
貴社の状況に合わせた最適な処理方法をご提案いたします。