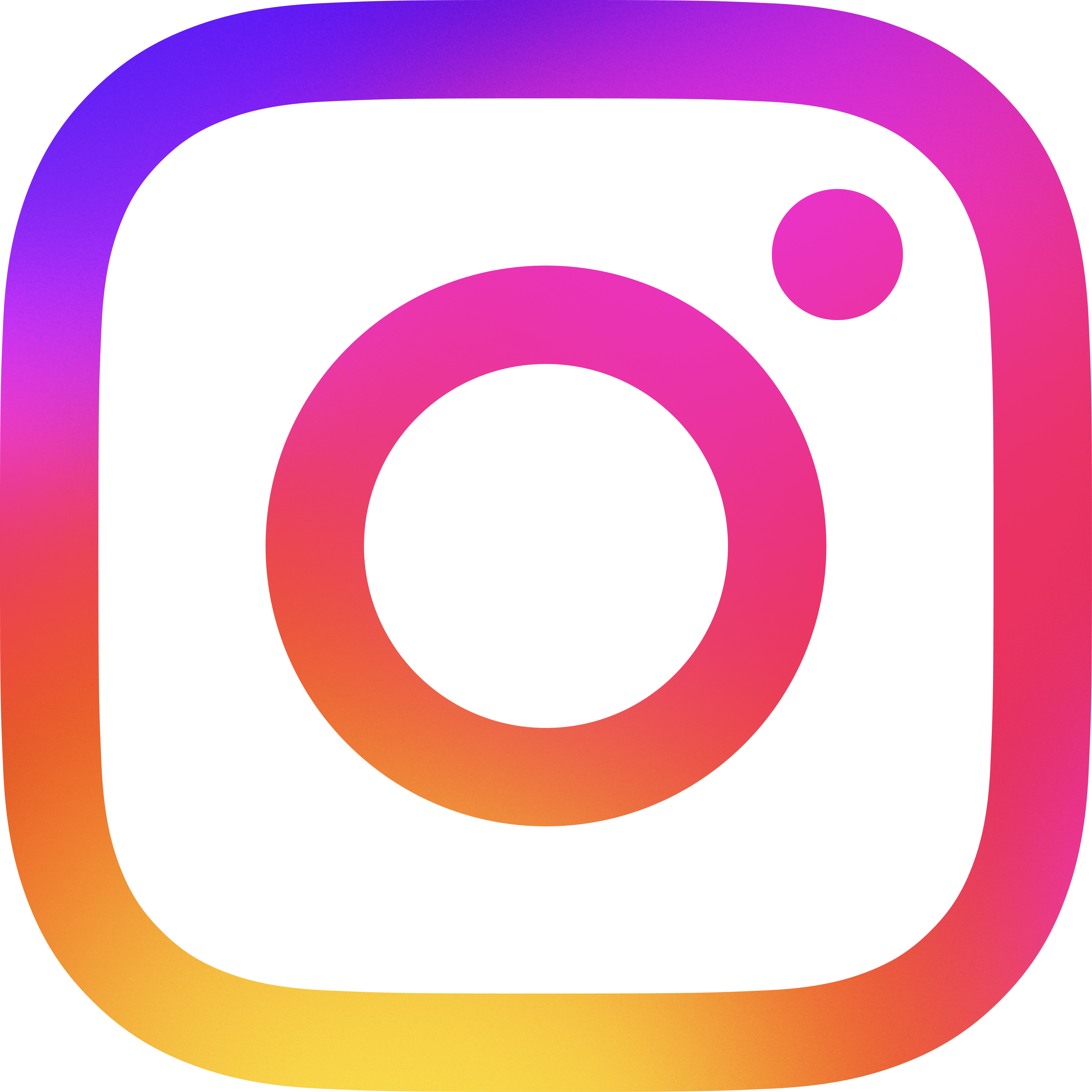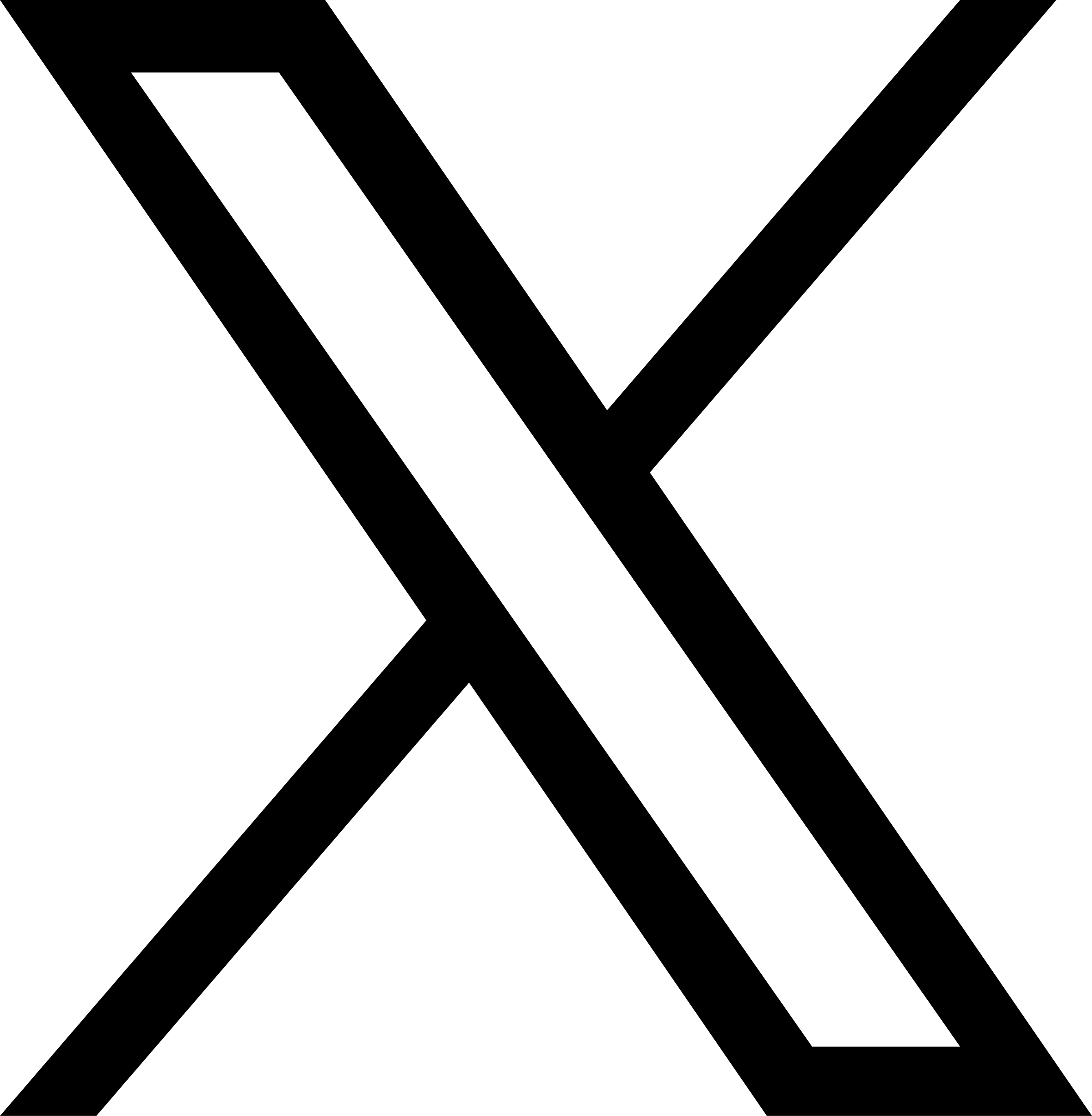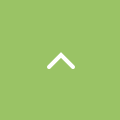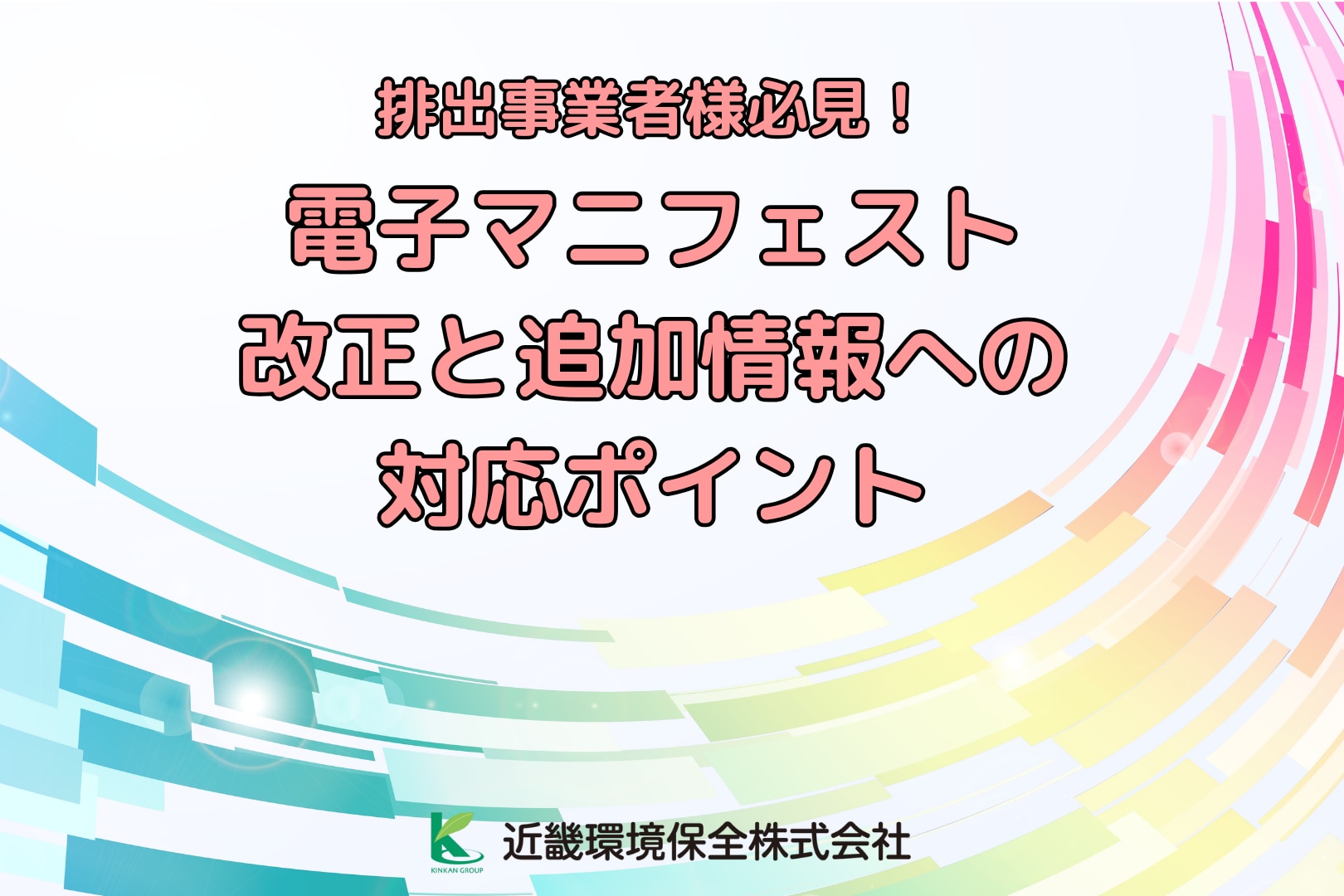
排出事業者様必見|2025年の電子マニフェスト改正と追加情報への対応ポイント
改正の本質と実務インパクトを徹底解説
2025年に入り、産業廃棄物処理に関する法制度の中でも、特に実務に大きな影響を与えるのが「電子マニフェスト制度の改正」です。
本改正は段階的に進められ、2025年4月からは努力義務としてスタートし、2027年4月以降には義務化される予定となっており、今のうちから対応を始めることが重要です。
今回の改正は単なる項目の追加にとどまらず、「廃棄物の見える化」「トレーサビリティの強化」「排出事業者と処理業者の責任明確化」といった目的があり、大きな転換点といえます。
これをチャンスととらえるか、対応漏れでリスクととらえるかで、企業の評価やコンプライアンス体制にも差が出るでしょう。
本コラムでは、電子マニフェスト制度の改正ポイントや実務上の注意点をわかりやすく解説します。
「うちはまだ紙マニフェスト」「対応が遅れているかも」と感じているご担当者様にも役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
電子マニフェスト制度の基本と改正の背景
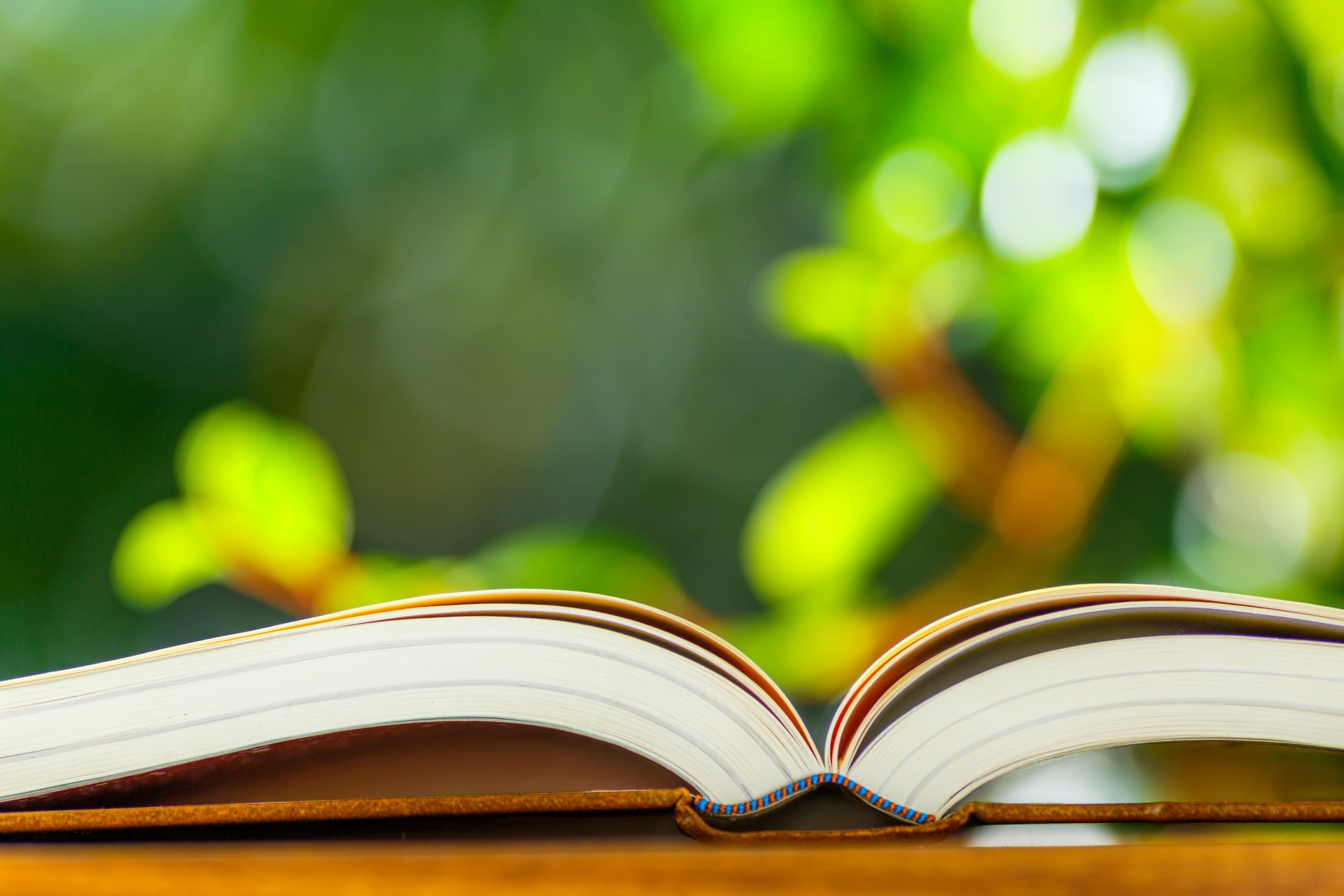
電子マニフェストとは何か
電子マニフェストとは、産業廃棄物の排出から最終処分までの流れを電子的に記録・管理する仕組みです。
従来の紙マニフェストに比べて、事務負担の軽減、報告義務の自動化、不正の抑止など、多くのメリットがあります。
環境省が推進するこの制度は、これまで一部の大企業を中心に導入が進んできましたが、中小企業ではまだまだ普及が進んでいないのが現実でした。こうした中で、2025年の改正は、電子マニフェスト利用の「標準化」へ向けた大きな一歩と位置づけられています。
改正の背景には何があるのか
2025年の電子マニフェスト制度の改正には、主に2つの大きな背景があります。
いずれも排出事業者にとっては「ただの制度変更」ではなく、今後の廃棄物管理のあり方そのものを見直すきっかけとなる重要なポイントです。
まずひとつ目は、「法令遵守の徹底と透明性の確保」です。
ここ数年、廃棄物処理に関する違反事例として目立ってきているのが、マニフェストに関する不適正な管理です。
具体的には、記載ミスや提出漏れ、期限超過、内容不備などがあげられます。
これらは決して悪意によるものばかりではなく、社内の連携不足や制度の理解不足による「うっかりミス」が原因となっているケースも多くあります。
しかし、排出事業者にとっては、たとえ意図的でなかったとしても、マニフェストに関する不備が行政処分の対象となる可能性は十分にあり、企業イメージの毀損や取引停止など、深刻な影響を及ぼすこともあります。
そうした背景から、マニフェスト制度全体の信頼性を高めることが急務となり、今回のような制度改正が行われたというわけです。
次にふたつ目の背景は、「カーボンニュートラル社会への移行」に向けた環境政策の流れです。
近年、環境配慮型経営は大企業だけでなく中小企業にも求められるようになり、SDGsやESGといったキーワードが広く浸透してきました。
これにより、企業は製品やサービスだけでなく、「廃棄物の処理・管理」まで含めた持続可能な運営体制を整えることが、社会的責任として期待されています。
特に、「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」という考え方のもと、廃棄物も“資源”として管理・再利用されるべきだという認識が広がりつつあります。
その中で、排出から最終処分に至るまでの処理フローの透明性やトレーサビリティ(追跡可能性)が、環境価値の指標のひとつとして扱われるようになっています。
こうした流れのなかで、電子マニフェスト制度の改正は、単なるIT化ではなく、企業の環境意識や社会的責任を「記録・可視化」するためのツールとして進化していると捉えることができます。
追加される5項目と、実務上注意したい“2つの関連情報”

追加された5つの項目
今回の制度改正により、電子マニフェストに処分業者が新たに入力すべき項目として、次の5つが追加されました。
- 処分業者の名称と許可番号
- 処分事業場の名称と所在地
- 処分方法(中間処理・最終処分)
- 処分方法ごとの処分量
- 処理後物の種類と量
これらはいずれも、処分業者が電子マニフェストに記録する内容です。
排出事業者が関わる関連情報への対応
これらの項目を正確に電子マニフェストへ反映させるためには、処理業者だけでなく、排出事業者からの正確な情報提供が不可欠です。
特に、以下のような情報は実務上の重要性が非常に高まっています。
廃棄物の性状
排出された場所
これらの情報が重要とされるのは、以下のような理由からです。
第一に、処分方法を正確に選定するためには、廃棄物の性状を把握しておく必要があります。
たとえば、油分を多く含む汚泥や、腐食性のある薬品系廃棄物などは、通常の焼却処理では対応できないケースがあります。有害物質の有無や性状の詳細が不明確なまま処分を依頼すると、適正処理が難しくなるだけでなく、法令違反となる可能性もあるため、事前の情報提供が不可欠です。
第二に、排出場所の情報は委託契約書や報告書類との整合性に関わるもので、マニフェストと実際の契約内容が異なる場合には、監査時に指摘される恐れがあります。
こうした情報を排出事業者が事前に提供することで、処分業者は正確に電子マニフェストへの項目へ入力が可能となります。
特に複雑な処理方法や複数の排出場所が関係する案件では、排出事業者からの的確な情報共有が、処理業者側の業務負担を大きく左右します。
また、情報が事前に揃っていれば、処分業者は現場での確認や再調整の必要がなくなり、結果として電子マニフェスト上の記録精度も向上します。
正確なマニフェストの作成は、後の行政対応や内部監査の場面においても信頼性の高い証拠となり、排出事業者にとってもコンプライアンス体制の強化につながる重要な要素といえるでしょう。
追加項目によって何が変わる?

ここからは、実際に電子マニフェストの項目が追加されることで、排出事業者の皆さまにとって何がどう変わるのかを、4つの視点でご説明します。
処分方法・処分量の把握が可能になる
これまでの電子マニフェストでは、処分先の事業者名と処理完了日などは確認できても、実際にどんな処理が行われ、どれだけの量がどう処分されたのかまでは記録されていませんでした。
今回の改正によって、具体的な処分方法(例えば焼却・破砕・中和など)や、その処分量が明示されることで、廃棄物の行方がより明確に見えるようになります。
再資源化物の種類・量の把握が可能
環境配慮型経営やESG報告を行う企業にとって、「どれだけ再資源化されたか」は重要な指標です。
今回の項目追加により、廃棄物がどれだけ再資源化されたかが記録されるようになり、サステナビリティレポートなどにも活用できるデータが取得可能になります。
二次処理以降の業者情報の可視化できる
中間処理業者の中間処理後に複数の2次処理先が存在するケースありますが、これまでは最終処分先までの情報が不透明になりがちでした。
今回の追加で、二次処理先の名称や所在が把握できるようになるため、「廃棄物がどこで、どう扱われたのか」を最後まで管理することが可能になります。
排出者自身による最終処分までの管理が可能
上記すべての項目が見えるようになることで、排出事業者として法的にも社会的にも説明責任を果たせるようになります。
コンプライアンスの強化につながるのはもちろん、取引先や監査先への信頼性向上にもつながる変化です。
まとめ|排出事業者にも求められる“体制の見直し”

今回の改正で法的な入力義務が直接的に課されるのは、処分業者です。
しかし、処分業者がその入力を正しく行うためには、排出事業者との円滑な連携が前提となります。
マニフェストの記載誤りがあれば、その責任の一端は排出事業者にも及ぶことになりかねません。
また、契約書やマニフェストの記載内容が一致しているか、廃棄物の分類や量、排出場所が明確に整理されているかといった“前提情報の精度”が、今後ますます重要になります。
この機会に、委託契約書、社内フロー、廃棄物の分類基準、処理業者との情報連携のあり方を見直してみてはいかがでしょうか?
電子マニフェスト改正は、単なる事務作業の変更ではなく、企業のコンプライアンスと信頼性を支える「見直しのチャンス」といえるのです。